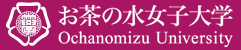担当授業科目
学部
「舞踊学概論」
大学で始めて受講する舞踊理論です。人間の存在を表現する舞踊は、その根源を人間の身体的・精神的・情緒的な構造にもっています。本講義では、このような舞踊について、歴史を縦糸に地域を横糸として人間にとっての舞踊の意義を多面的にとらえることを目標とします。
「臨床舞踊論」
2年次必修の講義課目です。人間の原初的な表現行為である身体表現を基盤に,より高次の精神・身体活動である舞踊の構造・機能を社会的・文化的文脈から講義します。具体的には、「身体」「感性」「表現」「創造性」「場」「コミュニケーション」等をキーワードに舞踊と人間の関わりを論じ、更に、そのような舞踊と人間の係わりが学校・病院・舞台等の様々な臨床場面にどのように現れるのかを具体的な事例に即して(例えば、振付家と踊り手との関係、踊り手と鑑賞者の関係、教師と子どもの関係等)解説します。そして、様々な臨床場面におけるその舞踊活動の内容と方法の検討、その有効性と課題の整理を通して、舞踊活動の意義を論じます。受講生は、本講義では舞踊と人間の関わりを理論的に理解し、且つ、その実践の概説を通して、舞踊を人間の存在の観点から見つめることを学びます。
「臨床舞踊論実験演習」
本演習では、臨床の現場(学校・病院・舞台・地域・スタジオなど)に現れる舞踊と人間の多面的な関わりを取り上げます。臨床現場での舞踊活動の観察、映像による観察、ならびに創造的芸術体験としての舞踊の活動に関する内外の文献の講読を行い、舞踊実践から得られた舞踊と人間の係わりと、それぞれの文献から得られた知見が、どのように結びつくのかを受講生各自が考察し、発表します。そしてその発表に対して、全員で討議を行い、問いの回しあいを通して、自分の研究の核となるキーワードを明確にしていきます。そのプロセスで、臨床の現場での舞踊活動を巡る諸課題について、実践的、科学的、哲学的に研究する様々な手法を学びます。
「舞踊教育法実習中等教育」
発想のトレーニングと身体の多様な動きの可能性の探究をベースに、舞踊の表現性に関する知識と技法を体得し、自己の内面を創造的に表現することへと導く方法を体験的に学びます。更に、個性の生きた個人創作とグループ創作の実習を通して、受講生自身の作品創作のための技術を磨くとともに,舞踊教育の学習内容とその指導方法、舞踊の見方,評価方法を理解し,指導方法を身につけていきます。毎時間の授業は、「ダンスウオーミングアップ・創る・踊る・みる」という活動から成っています。フォークダンスや現代的なリズムのダンスはダンスウオーミングアップの中で取り上げます。
「舞踊教育法実習初等教育」
自分のからだがどんな格好をして、どんな動きができるのかを探究し、そのような格好をしたり、動いた時、どんな気持ちがするのか、また、それを友達とした時にはどんな気持ちがするのか(動きとイメージとつながり)を体験的に理解し、表現運動の体験が、子どもの発達の諸側面とどのような関わりがあるのかを考察します。また,このような実習を通して,舞踊教育の学習内容とその指導方法を理解し,身につけていきます。
大学院前期課程
「舞踊表現学特論」
人間の原初的な表現行動である身体表現を基盤に,より高次の精神・身体活動である舞踊の構造・機能を社会的・文化的コンテクストの中で捉え,美学からみた舞踊と、舞踊経験からみた舞踊という視点から舞踊の本質について論じます。その上で,その本質を踏まえた舞踊表現の様々な実践活動の実態と可能性について討議し、舞踊経験に基づいた舞踊理論の生成について考察します。
「舞踊表現学演習」
舞踊表現学特論の講義内容に関わって,舞踊に関する内外の文献の購読及び映像観察・分析を通して、舞踊表現の研究方法に関する演習を行います。そして,各自の関心に応じた舞踊表現を対象として,舞踊映像を取り入れてのレポートの作成を求めます。
大学院後期課程
「舞踊表現特論」
舞踊文化研究、舞踊教育研究、舞踊療法研究及び感性コミュニケーション研究などの学問領域に関する国内外の学術雑誌を対象に、舞踊表現に関する最近の研究動向を紹介し、その研究成果の分析及び舞踊研究の方法論の整理・再検討を行う。その上で,研究対象とする舞踊表現を論ずるにふさわしい研究手法を再考し、そこで対象とする舞踊表現を通して人間と舞踊の関わりを探求するための具体的なテーマの設定及び複眼的な研究手法を学ぶ。
「舞踊表現特論演習」
感性的コミュニケーションや舞踊に関する内外の文献の講読及び映像観察・分析を通して,舞踊表現の研究方法に関する演習を行い,各自が実際に舞踊映像を取り入れてパワーポイントでのプレゼンテーションを行う。また、同時に舞踊表現活動の援助や指導に関する能力を養うために、フィールドでの舞踊表現活動を実践し、更に、その実践を事例として前述の方法で研究し、プレゼンテーションを行う。このように演習では、理論と実践のバランスのとれた人材養成を目指して、理論研究とフィールドでの実践を繰り返し行う。